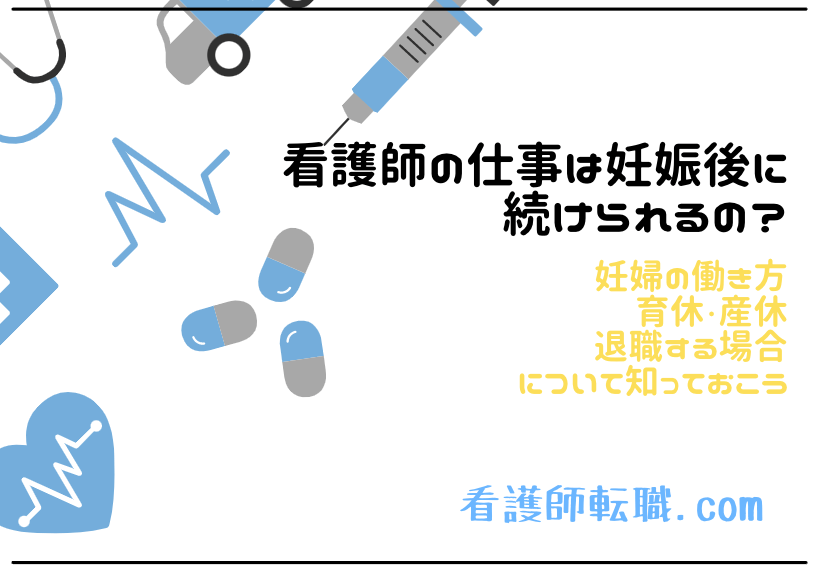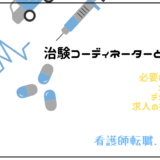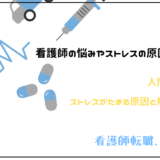女性は妊娠がわかると嬉しい半面、仕事を続けられるかどうか不安に感じる人も多いのではないでしょうか。
特に人手不足に悩まされている医療施設で働く看護師の場合、職場の状況を考えるあまりに産休の取得や業務の軽減を言い出せず、母体に負担がかかってしまうことがあります。
 看護ちゃん
看護ちゃん
今回は、妊娠しても安心して仕事を続けるために、看護師が気をつけておきたいことをご紹介します。
妊娠が発覚したらどうすればいい?
妊娠が発覚して気になるのが、今後の仕事についてではないでしょうか。
勤務先へ迷惑をかけないためにも、まず何を決めれば良いのか知っておきましょう。
出産前後のことを考える
妊娠がわかったら、できるだけ早いタイミングで復職するか、退職するのかを決めるようにしましょう。
出産後も看護師として働く場合は、産休や育休といった勤務先の制度を確認しておく必要があります。
産休は、非常勤でも常勤でも取得できるものですが、申請を出さなければ出産間際まで働くことになります。
 看護ちゃん
看護ちゃん
病院によっては、母体に負担がかかる夜勤の免除や時短での勤務が認められることもあります。
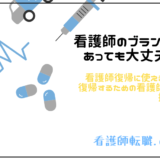 看護師のブランクがあっても大丈夫?!看護師復職に使える支援・看護師復帰するための看護師求人の探し方
看護師のブランクがあっても大丈夫?!看護師復職に使える支援・看護師復帰するための看護師求人の探し方
上司に報告するタイミングは?
職場に迷惑がかからないよう、妊娠がわかった時点で速やかに上司に報告することをおすすめします。
妊娠の報告を受けたら、勤務先は必要に応じてシフトの変更やスタッフの補充を行うことになるでしょう。
まずは師長など直属の上司に妊娠を伝え、今後の勤務時間や働き方、産休について相談しておくことが大切です。
 看護ちゃん
看護ちゃん
退職をする場合は、自分の意思をはっきりと伝えてから、退職時期を相談しましょう。
もちろん、妊娠が発覚しても、すぐに産休に入ったり退職したりするわけではありません。
では妊娠中に業務に携わるときは、どのような点に気をつければ良いのでしょうか。
妊娠中の働き方はどのように変わるの?
妊娠中は体調が安定せず、思うように業務をこなせないこともよくあります。
働き方について、注意点などをご紹介します。
妊娠中に働くときの注意点
妊娠中はお腹が大きくなるにつれて体にも負担がかかります。
仕事中の思わぬ事故を防ぐためにも、重たいものを持つなどの力仕事は避けたほうが良いでしょう。
また、病院は衛生管理ができているとはいえ、流産の危険性がある妊娠初期は患者さんの感染症がうつらないよう気をつける必要があります。
インフルエンザ・コロナなどの感染症には注意しましょう。
「男女雇用機会均等法」の第13条では、働く女性が安心して出産に臨めるよう
「雇用している女性が検診を受けて医師から指導を受けた場合、事業主はその指導を守れるように、勤務時間の変更や、勤務の軽減など措置を講じなければならない」
とされています。
職場における男女の差別を禁止し、募集・採用・昇給・昇進・教育訓練・定年・退職・解雇などの面で男女とも平等に扱うことを定めた法律のことです。1985年制定され、翌86年より施行されました。その後、97年に一部改正され、女性保護のために設けられていた時間外や休日労働、深夜業務などの規制を撤廃。さらにセクシャル・ハラスメント防止のため、事業主に対して雇用上の管理を義務づけています。
通勤・帰宅ラッシュ時の電車やバスは人が多く体を押されるほか、長時間立っていなければならない場合もあります。
 看護ちゃん
看護ちゃん
また、「つわり」が酷い場合などには、勤務時間の短縮や休憩時間の延長、仕事量の軽減を申し出ることも可能です。
ただし、職場の事情によっては、つわりが酷くてつらかったり、切迫流産で安静にする必要があったりしても、なかなか休めないことがあります。
その場合はかかりつけの主治医に「母性健康管理指導事項連絡カード」に記入してもらい、事業主に提出して対応してもらいましょう。
夜勤はいつまで、できるものなの?
特に注意を払いたい期間は、妊娠15週までの初期と28週から出産までの後期。
赤ちゃんの胎盤ができる妊娠初期は、ホルモンバランスが変化し、お腹の痛みや張りなどの症状が出やすい時期です。
つわりの症状がある人もいます。
業務中に症状が出て、周囲に迷惑をかけてしまう可能性があります。
 看護ちゃん
看護ちゃん
なお、妊娠12週から22週までの間に起こり得る後期流産は、母体の異常が原因で起こることが多いとされています。
疲れやストレスが流産の引き金となることもありますので、心身ともに疲労をためないようにしましょう。
妊娠後期になるとお腹が大きく、重たくなります。
妊娠が発覚したら夜勤は避けた方がいい
出産が予定日より早まるケースもあり、何が起こるかわかりません。
夜勤はできれば避けたほうが良いでしょう。
看護師の中には、妊娠が発覚してすぐに夜勤の免除を申し出る人もいます。
上司に早めに相談し、妊娠初期は夜勤から外してもらう、勤務時間を短縮してもらうなどの対策を取ることをおすすめします。
なお、妊娠中の労働時間について「労働基準法」の第66条では「妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはならない」と定められています。
施設の方針によりますが、夜勤は避けた方がいいでしょう。
それでは、産休はいつから取得できるように決まっているのでしょうか。
産休はいつから取得できるの?
産前休業と産後休業のことを表す産休は、働く女性なら雇用形態に関係なく、誰でも取得する権利があります。
産前産後休業については労働基準法 第65条で定められています。
産前休業の期間は、予定日を含む出産前6週間(双子など、2人以上の子供を同時に妊娠している場合は14週間)からです。
取得が義務付けられているわけではないため、「本人から休業の申請があった場合は働かせてはいけない」というものです。
反対に、本人が希望しない場合は出産ギリギリまで働くことができます。
産後の休業期間は、出産してから8週間です。
 看護ちゃん
看護ちゃん
ただし、主治医の許可があり、本人が希望すれば産後6週間で働くことができます。
また、子供が1歳になるまでに復職した場合は、1日2回、各30分の「育児時間」を請求できます。
勤務時間の始めや終わりに使ったり、まとめて1時間取ったりすることも認められています。
では、産後休業が終了した後、育児休業(休暇)の取得は認められているのでしょうか。
育休はどのくらい取得できるの?
1歳に満たない子供がいる場合、子供が1歳になるまでの間、本人が希望する期間を休業することが認められています。
派遣や契約社員として雇用されている場合は、申請時点で同じ事業主に1年以上雇用されていること、子供の1歳の誕生日以降も雇用される見込みがあることなどが条件となっています。
このように、産休や育休は申請すれば取得できるように法律で定められています。
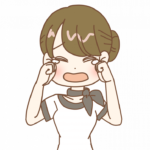 看護ちゃん
看護ちゃん
退職する場合のタイミング
最後に、看護師が妊娠をきっかけに退職を考える理由や、タイミングを見ていきましょう。
退職を考える理由
妊娠中でも看護師の仕事を続けることは可能ですが、職場の状況や体制によっては退職を選ぶ看護師も少なくありません。
退職を選ぶ理由としては、
- つわりが重く仕事ができない
- 育児に専念したい
- 体力的に問題がある
などが挙げられます。
また、女性が多い職場だからといって、必ずしも産休や育休に理解があるとは限りません。
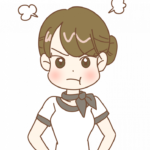 看護ちゃん
看護ちゃん
妊娠をきっかけに先輩や同僚との人間関係がギクシャクしたり、不当な扱いを受けるマタニティハラスメントに悩んだりすることもあります。
退職の時期はいつ?
退職を選択する場合は、引き継ぎ期間を考慮して、退職希望日の1カ月~3カ月前には上司に伝えるようにします。
妊娠がわかった時点で退職を決めているなら、妊娠の報告と同時に伝えたほうが良いでしょう。
円満退職をするためにも、退職の決断をした場合速やかに上司に報告するようにしましょう。
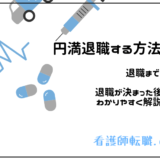 看護師の転職で円満退職する方法は?退職までの流れ・マナー・退職が決まった後のことを解説します
看護師の転職で円満退職する方法は?退職までの流れ・マナー・退職が決まった後のことを解説します
妊娠中の看護師には周囲の理解とサポートが不可欠
看護師として忙しく働いていても、妊娠や出産は難しいことではありません。
しかし、ウイルスに感染する危険性があったり、力仕事があったりするなど、看護師業務は妊婦にとってリスクのある仕事でもあります。
自分自身とお腹にいる赤ちゃんを守るためにも、危険性のある業務からは外してもらうようにお願いする勇気も必要です。
勤務時間の変更や業務の軽減など、同僚や先輩に協力してもらうことも多くなりますので、日頃から周囲への配慮を欠かさないようにしておくといいかもしれません。